-
飲食店の運営
「店をたたむ」と決断したら|飲食店オーナーが知っておくべき手続きの流れと再出発の選択肢

飲食店経営は売上の波が大きく、時には「店をたたむ」という決断が必要になることもあります。計画的に閉店作業を進め、次の挑戦へつなげるためには、必要な手続きの内容や流れをあらかじめ把握しておくことが大切です。
この記事では、飲食店をたたむ際の手続きや閉店にかかる費用、再出発の選択肢について解説します。具体的なステップや注意点を理解することで、不要なやりとりやトラブルを防ぎ、余裕を持って次なる一歩を踏み出すことができます。
「店をたたむ」前に知るべきサイン

-
飲食店経営を続けるなかで、撤退を検討すべきサインはいくつか存在します。閉店・廃業する飲食店にはどのような兆候があるのか、ここでは「店をたたむ」前に知るべき4つのサインを紹介します。
看板メニューの売上が落ちている
集客の柱ともいえる「看板メニュー」の売上が落ちている場合、お店の魅力や強みが薄れ、集客力が低下しているサインといえます。これまで人気だった看板メニューの売れ行きが悪くなるのは、味や品質の劣化、顧客ニーズやトレンドの変化、競合店の登場などさまざまな要因が考えられます。
全体の売上が許容範囲にあるなら、すぐに「店をたたむ」決断に直結することはないかもしれません。しかし、そのまま放置するといずれは他のメニューにも悪影響が及ぶおそれがあるため、メニューの改良や販促強化といった対策を早急に打ち出す必要があります。
赤字が慢性化している
数か月にわたり赤字が続いている場合は、店舗を維持するための運転資金が急速に枯渇し、いずれは「店をたたむ」決断を余儀なくされるでしょう。無理に営業を続けることは経営リスクを増大させ、資金不足による支払遅延やトラブルの発生など、深刻な問題を引き起こすおそれがあります。
まずは原価管理やメニュー改定、固定費の見直しなどで改善の余地があるのか検討し、それでも黒字化の兆しが見えない場合には早めに撤退を判断するほうが、その後の再出発の可能性が広がっていくと考えられます。資金不足はスタッフや取引先へ与える影響が大きいため、早めに現状を把握し、撤退も視野に入れた判断を下すことが重要です。
店内の清掃が行き届いていない
-
QSC(品質・サービス・清潔さ)は、飲食店が重視すべき基本的な要素です。清掃が十分に行き届いていない状態は、見た目の印象や顧客からの信頼を損なうだけでなく、経営者やスタッフのモチベーション低下を映し出すサインともいえます。
忙しさで掃除が後回しになっていることも考えられますが、そのまま放置すれば店内の雰囲気は確実に悪化します。清潔感のない店舗は顧客からのクレームに直結しやすく、ネガティブな口コミが広がれば新規顧客の来店が減少し、いずれは常連客の離脱も招くことになるでしょう。
-
常連客が離れている
-
安定した売上の基盤となる「常連客」が離れるのは、顧客ニーズとのズレが進行しているサインであり、改善しなければ「店をたたむ」判断が現実味を帯びてくるでしょう。常連客は不満があってもすぐに店を離れるのではなく、具体的な要望や改善点を伝えてくれることが多いため、その声を“改善のヒント”として真摯に受け止めることが大切です。
ただし、立地や周辺環境の変化などに起因し、客層が入れ替わっていることも考えられます。この場合は新しいターゲット層に合わせたメニュー開発や情報発信を行うことで、売上を維持・回復できる可能性があります。
「いつ閉めるか」が再出発のカギ−適切なタイミングとは?
再出発を成功させるためには、次の挑戦への余力を残すことが重要です。あらかじめ撤退ライン(=損切りライン)を決めておくと、売上や利益が一定水準を下回った時点で「撤退するか否か」を客観的に判断できます。閉店・廃業するにも費用がかかるため、その資金を確保できる段階で撤退を決めるのが望ましいでしょう。
また、体力や気力が十分にあるうちに判断することで、閉店後も冷静に次の挑戦に取り組む余裕が生まれます。再出発をスムーズに進めるためにも、損失を最小限に抑えられるタイミングを見極めることが大切です。
店タクは飲食店オーナーが抱える店舗運営の悩みを「職人と組む」ことで解決するサービスです。「店をたたむ」と決断する前に、業務委託でつながる「新しい店舗運営」を検討してみませんか。
店をたたむときの手続きと閉店費用
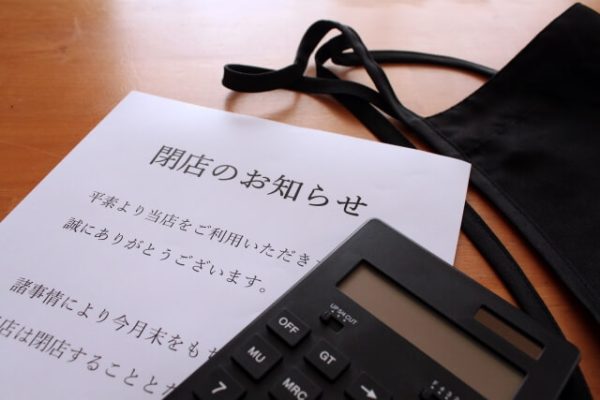
-
飲食店を閉めるときには多くの手続きを伴い、閉店にかかる費用を事前に用意しておく必要があります。ここでは、店をたたむときの準備と手続きの流れ、閉店費用について解説します。
-
店をたたむ前にするべき準備
-
店をたたむ前には、関係各所への通知や手続きを計画的に行うことが重要です。
- ・スタッフへの解雇通知
- ・不動産会社への解約通知
- ・仕入れ先やリース業者など取引先への通知
- ・電気・水道・ガス・インターネットなどの解約手続き(最終使用日の調整)
- ・顧客への告知
特に注意すべきはスタッフへの対応です。使用者が労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇を予告する必要があります(労働基準法第20条より)。これを怠り、解雇の予告を行わない場合には、30日以上分の平均賃金を「解雇予告手当」として支給しなければなりません。また、解雇予告の日数が30日に満たない場合も、その不足日数分の平均賃金を支払う必要があります。
店をたたむときの手続きの流れ
閉店・廃業当日以降は、店舗の原状回復や設備の撤去・返却を行うほか、さまざまな行政手続きが必要となります。それぞれ提出期限が決められているため、事前に内容を確認し計画的に進めていくことが大切です。
- 閉店・廃業に伴う手続き(一例)
提出期限
届出書(提出先)
廃業日から5日以内
健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届(年金事務所)
健康保険・厚生年金保険被保険者喪失届(年金事務所)
廃業日から10日以内
廃業届/食品営業許可証の返還(保健所)
事業開始(廃止)等申告書(都道府県税事務所)
廃業日翌日から10日以内
雇用保険適用事業所廃止届(公共職業安定所)
雇用保険被保険者資格喪失届(公共職業安定所)
雇用保険被保険者離職証明書(公共職業安定所)
廃業日から1か月以内
個人事業の開業・廃業等届出書(税務署)
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(税務署)
廃業日翌日から50日以内
労働保険確定保険料申告書(労働基準監督署)
廃業後速やかに(※)
消費税の事業廃止届出書(税務署)
防火管理者選任(解任)届出書(消防署)
※法的期限はないものの、遅滞なく速やかに届け出る必要がある
閉店にかかる費用
閉店・廃業時にかかる主な費用は次のとおりです。
- ・原状回復費
- ・退去までの家賃
- ・リースの残額料金
- ・廃棄処分費
- ・後払いの経費や借入金の返済
- ・解雇予告手当(必要な場合)
これらの費用は閉店に伴って発生するため、あらかじめ資金を確保しておくことが重要です。保証金が返還される場合は実質的にプラスになることもありますが、物件を明け渡したあとに返ってくるお金であるため、当面必要となる費用は自己資金で賄えるよう準備しておきましょう。
【飲食店向け】再出発の選択肢とその手順
「店をたたむ」ことを決断しても、すぐに完全撤退するのではなく、店舗や事業を活かしながら再出発を目指す方法もあります。その代表的な選択肢として挙げられるのが「業態転換」と「運営委託」です。
再出発の選択肢①:業態転換
業態転換とは、より収益性や需要のある形態に切り替える方法です。市場ニーズに合わせた新しい業態に挑戦することで、既存の店舗資産や経営ノウハウを活かしながら新しい顧客層を取り込み、経営改善につなげられる可能性があります。
飲食店における業態転換の基本的な手順は次のとおりです。
- 1.市場調査と現状分析
- 2.コンセプト・事業計画の策定
- 3.オペレーションの設計
- 4.実行・評価
これらのステップを踏むことで、感覚的な判断ではなく、データや計画に基づいた転換が可能になります。新業態を安定させるためには、リリース後も定期的に評価し、必要に応じて改善を重ねることが大切です。
再出発の選択肢②:運営委託
運営委託とは、自らは運営から退き、信頼できる第三者に店舗運営を任せる方法です。「店は残したいが、自分で運営するのが難しい」と感じている経営者にとって有効な選択肢となります。
飲食店における運営委託の基本的な手順は次のとおりです。
- 1.委託先の選定
- 2.契約内容の取り決め(必要に応じて内見・打ち合わせを実施)
- 3.業務委託契約の締結
- 4.運営開始と定期的なフォロー・評価
運営委託では、信頼できる委託先を選定し、双方合意のもとで報酬や営業ルールを取り決めるのが一般的です。飲食店の業務委託については以下の記事で詳しく解説していますので、運営委託を検討する際の参考にしてください。
関連記事:飲食店が業務委託をするメリット・デメリットとは?雇用契約との違いを詳しく解説
まとめ
飲食店の閉店・廃業には、関係各所への届出やスタッフへの告知、原状回復工事などさまざまな手続きを伴います。再出発を目指す場合は、体力や気力、資金が残っているうちに「店をたたむ」決断を下すことが重要です。
また、完全にお店を閉じる前に、業態転換や運営委託で再挑戦する選択肢も考えられます。既存の店舗やノウハウを活かしつつ、新しい市場や顧客ニーズに柔軟に対応することで、事業を継続できる可能性が高まるでしょう。どの方法を選ぶにせよ、閉店の決断も戦略の一つと捉え、次の挑戦に向けて前向きに行動することが大切です。
店タクでは「店舗運営を任せたいオーナー」と「腕のある職人」とのマッチングを支援しています。自分で経営を続けるのは難しいと感じている場合は、信頼できる職人に店舗運営を委ねるという選択肢もあります。
-
 飲食店運用のヒント
飲食店運用のヒント