-
飲食店の運営
飲食店の間借りとは?オーナー側のメリット・デメリットや収益相場、貸し出しの流れを解説

飲食店の間借り営業は、オーナーにとって店舗の空き時間や遊休スペースを有効活用できる手法です。しかし、間借りは責任の所在が曖昧になりやすく、営業許可を持つオーナーがトラブルに対する責任を負うケースが多いため、貸し出す前に契約条件や運営ルールを明確に取り決めておく必要があります。
この記事では、間借りを提供するオーナー側のメリットやデメリット、収益の目安、貸し出しの流れについてわかりやすく解説します。
飲食店の間借りとは
飲食店の間借りとは、既存店舗の厨房や客席スペースを、一定の時間帯や条件で他の料理人が借りることをいいます。例えば、ディナータイムのみ営業しているレストランを借りて、昼の時間帯にピザやハンバーガーを販売するケースが挙げられます。一つの店舗で異なる形態の飲食店が時間帯を分けて営業できるため、借りる側は開業資金を抑えながら少ないリスクでの出店が可能です。
一方、既存店舗のスペースを他者に貸し出すことは「間貸し」といいます。つまり、「間借り」はお店を借りる側の呼び方であり、「間貸し」はお店を貸し出す側、すなわち既存店舗のオーナーの立場から見た表現となります。オーナーにとっての間借り営業は、自店の営業時間外や空いているスペースを有効活用する手段であり、間貸しによって本業とは別の収益を得ることができます。
間借りスペースを提供するメリット
使っていないスペースを柔軟に活用できる方法として注目される間借り営業。一定の条件で店舗を間貸しすることで、飲食店オーナーは以下のようなメリットを享受できます。
- ・副収入を得られる
- ・遊休スペースを活用できる
- ・固定費の負担を軽減できる
- ・店舗の集客力が高まる
これらのメリットについて以下で詳しく解説します。
副収入を得られる
飲食店の間借り営業は、オーナー側にとって「営業していない時間」や「使用していない空間」を収益化できる方法です。自分の本業に影響が及ぶことなく、利用料や売上歩合などの副収入を得られるのが大きな魅力です。
借りる側にとっても、初期費用を抑えながら自分のお店をオープンできるため、双方にとってメリットのある仕組みといえます。
遊休スペースを活用できる
飲食店が間貸しを行うことで、営業時間外や定休日にも自店のスペースが有効活用され、店舗全体の稼働率を高めることができます。稼働率が向上すると、単に収益が増えるだけでなく、固定費の負担軽減やリスクの分散にもつながり、長期にわたって安定した営業を続けられる可能性が高まります。
間借りを活用する料理人にとっても、既存店舗の設備やスペースをそのまま利用し、すぐに営業を始められるメリットがあります。オーナーにとっては遊休スペースの活用で稼働率を高め、借り手にとっては既存店舗を活かして開業のハードルを下げる、双方にとって効率的な手法となります。
固定費の負担を軽減できる
間借りスペースを提供することで、店舗の家賃や光熱費などの固定費の負担を軽減できます。店舗の固定費は営業時間外でも発生するため、空き時間にスペースを貸し出して収益を得ることで、費用をカバーしつつ経営の安定化につなげられます。
借りる側も賃料に加えて光熱費の一部を負担するケースが多いものの、新たに飲食店を開業する場合と比べると、初期費用や維持費を大幅に抑えることができます。これにより、オーナーは安定した経営、料理人はコストを抑えた営業と、それぞれのニーズを満たす形になるでしょう。
店舗の集客力が高まる
間借りによって既存店舗とは異なる形態のお店がオープンすることで、店舗全体の話題性や集客力が高まる可能性があります。例えば、昼間は手軽なランチを求める層、夜は本格的な料理やお酒を楽しみたい層など、時間帯によって顧客層が変わることで幅広いターゲットにアプローチでき、結果的に店舗全体の認知度やリピーターの増加につながりやすくなります。
借り手にとっても、既存店舗の立地や知名度を活かして集客できるため、双方にとってメリットのある関係が築けるでしょう。
間借りスペースを提供するデメリット

-
飲食店の間借り営業は、貸し手・借り手の双方にメリットのある取り組みですが、オーナー視点では注意すべきデメリットも存在します。
- ・トラブル発生のリスクがある
- ・店舗ブランドに悪影響が及ぶ可能性がある
- ・各種許認可や保険の確認が必要となる
- ・設備の消耗・破損リスクが増える
これらのデメリットについて以下で詳しく解説します。
トラブル発生のリスクがある
間借りスペースを提供する場合、既存店舗に影響を及ぼすトラブルが発生する可能性があります。営業許可を持つオーナーは、間借り店舗で起きたトラブルの責任を負うケースが多いことに注意が必要です。
具体的には以下のようなリスクが考えられます。
- ・衛生問題や接客態度に関するクレーム
- ・売上精算や歩合金額の計算ミスによる金銭トラブル
- ・備品・設備の破損による修理費の発生
- ・営業ルール違反による契約トラブル
これらはオーナーの店舗運営にも直接影響するため、事前に契約書で責任範囲や利用ルールを明確に定めるとともに、運営中のチェック体制も整えておく必要があります。
店舗ブランドに悪影響が及ぶ可能性がある
間借り営業で提供される料理やサービスの質が低い場合、既存店舗のブランドイメージにも悪影響が及び、客足が減ってしまう可能性があります。異なるお店を運営していても、借り手の管理が不十分だと、オーナー自身が思わぬトラブルやクレームの対応を迫られるリスクがあるのです。
こうした状況を避けるには、借り手を選定する際にメニュー内容や品質管理、サービスレベルなどを確認し、安心して間貸しできる店舗を選ぶことが重要です。
各種許認可や保険の確認が必要となる
飲食店の営業には「飲食店営業許可」のほか、店舗の形態や営業内容に応じて必要な許認可があります。既存店舗の許可で対応できない場合には新たに取得する必要があるため、食品衛生責任者や防火管理者などの設置も含めて事前に確認しておかなければなりません。こうした許認可手続きや衛生管理を徹底しなければ、保健所から指摘を受けるリスクがあります。
また、既存店舗の保険(火災保険や施設賠償責任保険など)に関しても、間借り営業での使用がカバーされるかどうかを事前に確認し、場合によっては保険内容の見直しや追加加入を検討する必要があります。
設備の消耗・破損リスクが増える
間借りによって設備の使用頻度が増えると、自店だけで使うよりも消耗しやすく、破損リスクが増えることが考えられます。設備が破損した場合、その修理費用や交換費用はオーナーが負担するケースが多いため、間借り店舗との契約条件で原状回復や損害補償の基準を明確にしておくことが重要です。加えて、備品や設備の管理に関するルールをあらかじめ共有し、借り手が適切に使用できるようにしておくのが望ましいでしょう。
新しい飲食店の運営を提案する「店タク」では、飲食店オーナーが独立志向のある料理人に店舗運営を委託することを推奨しています。エリア・業態・売上目安などから、お店の現状や条件にマッチするベストパートナーを見つけることができます。
間借り飲食店の収益相場
間借りスペースを提供する飲食店は、具体的にどのくらいの収益が見込めるのでしょうか。ここでは、賃料の目安や売上歩合の相場など、オーナー視点で間借り営業の収益について解説します。
賃料・利用料の目安
-
間借りスペースの賃料は、都心部で月額10万円程度が目安となります。
また、1日単位で借し出す場合は3,000〜10,000円程度が一般的です。
ただし、貸し出す時間帯や立地条件、店舗の規模、設備の充実度など、さまざまな要素によって目安となる料金は大きく変動します。
売上歩合の相場
-
賃料や固定費の按分に加えて、売上の一定割合をオーナーが受け取る歩合制を採用することがあります。需要の高いエリアでは20%以上になることもありますが、一般的には売上の10〜15%程度が相場といわれています。
【補足】既存許可を使う場合
既存の営業許可を利用して間借りを行う場合、営業主体はあくまで既存店舗のオーナーとなります。間借り店舗の売上もオーナーのものとして扱われるため、借り手である料理人には「報酬」として支払う形が一般的です。
飲食店を間借りで貸し出すときの流れ
飲食店の間貸しは次の5つのステップで段階的に行います。
さまざまな確認事項や取り決めが発生するため、事前にルールや責任の範囲を明確にしながら計画的に進めることが大切です。
- 1. 物件オーナーに間貸しの承諾を得る
- 2. 必要な許認可・保険を確認する
- 3. 利用料・契約条件・共通ルールを決める
- 4. 間借りしたい料理人と契約を結ぶ
- 5. 運用を始める
物件オーナーに間貸しの承諾を得る
店舗を借りて営業している場合、まずは物件を所有するオーナーや管理会社に対して間貸し営業の承諾を得なければなりません。賃貸借契約で転貸や用途変更を禁止しているケースでは、承諾を得ずに間貸しを行うと契約違反となり、契約解除や損害賠償の請求を受けるリスクがあります。
必要な許認可・保険を確認する
間貸しの承諾を得たら、間借り営業に必要な各種許認可や保険の適用範囲を確認します。営業形態が異なる場合など、既存店舗の営業許可を利用できない場合は、間借り営業を行う飲食店が新たに営業許可を取得する必要があります。
利用料・契約条件・共通ルールを決める
店舗を間貸しできる体制が整ったら、間借り店舗の賃料や売上歩合、利用時間帯、設備の管理方法、原状回復の基準などを決定します。こうした条件やルールを契約書に明記することで、双方の責任や役割が明確になり、トラブルを未然に防ぐことにつながります。
間借りしたい料理人と契約を結ぶ
借り手となる料理人との間で契約を締結します。契約段階で条件やルールを細かく確認し、双方が納得したうえで契約を結ぶことが重要です。
運用を始める
契約が整ったら運営開始となります。既存店舗のオーナーも定期的に運営状況を確認し、設備の使用方法や衛生管理に不備がないかをチェックします。必要に応じて相談や情報共有を行うなど、双方で適切なコミュニケーションを取ることが求められます。
飲食店の間貸しを考えているなら「業務委託」がおすすめ

-
飲食店の業務委託(運営委託)とは、既存店舗の経営をオーナーが主体となって継続しつつ、実際の運営を料理人に委託する形式のことです。
間借り営業は空き時間やスペースを有効活用できる反面、衛生管理や設備管理などの責任がオーナーに集中しやすいという課題があります。一方、業務委託では営業許可や経営責任がオーナー側にあり、委託先はあくまで運営業務を担う立場のため、リスクをコントロールしやすいのが特徴です。
店舗運営を腕のある料理人に任せることで、オーナー自身は経営戦略や売上管理といったコア業務に専念できます。「店舗は維持したいが、自分で営業する時間や人手が足りない」というオーナーにとって、業務委託は現実的かつリスクの少ない選択肢となります。
飲食店の業務委託については以下の記事でも詳しく解説していますので、本記事とあわせて参考にしてください。
関連記事:飲食店が業務委託をするメリット・デメリットとは?雇用契約との違いを詳しく解説
-
まとめ
飲食店オーナーにとって、間借り営業は自店のスペースを有効活用し、本業とは別の収益を得られる手段です。しかし、一つの店舗で異なる形態の営業を行うと、さまざまな面で責任が曖昧になりやすく、予期せぬトラブルやクレームが発生するリスクが高まります。
リスクを避けつつ安定経営を図るには、腕のある料理人に運営業務を任せる「業務委託」を採用するのがおすすめです。この方法なら、オーナーが日々の調理や接客から離れても、店舗の看板を維持しながら安定した収益を確保できます。自身は経営に専念し、戦略的に店舗を成長させたいオーナーに最適な選択肢となるでしょう。
店タクは「お店を任せたい人」「経営に挑戦したい人」を業務委託という仕組みでつなぐ新しいマッチングサービスです。飲食店の間貸しを考えているなら、信頼できる第三者に店舗運営を委託する選択肢もぜひご検討ください。
-
飲食店の運営
飲食店における人件費の目安とは?失敗しないコスト最適化の方法を詳しく解説

飲食店経営において、人件費は売上の大きな割合を占める重要なコストです。人件費が高すぎると利益が圧迫され、低すぎるとサービス品質や従業員満足度に影響が及ぶため、適切なバランスで管理することが求められます。それでは、経営上のリスクやトラブルを防ぎつつ、人件費を最適化していくにはどうすればよいのでしょうか。
この記事では、飲食店における人件費の目安とともに、失敗しないコスト最適化の方法を詳しく解説します。人件費の抑制は短期的には利益を生む一方で、現場に過度な負担を強いる恐れがあるため、安易な削減に踏み切らないことが重要です。
人件費とは
人件費とは、企業や店舗が事業を運営するうえで必要となる「人材」に関わる経費全般を指します。従業員の労働に対して支払われる給与のほか、賞与や福利厚生費、教育・研修費、退職金なども含まれます。一般的には「固定費」として扱われますが、繁忙期の対応で一時的に人員を増やす場合など、売上や状況に応じて柔軟に変動できる側面もあります。
飲食店においては食材費と並ぶ大きな経費であり、人件費の内訳や比率を正しく把握・管理することが健全な店舗経営につながります。適切な人件費管理は、過剰なコストを抑えて利益を確保するとともに、サービス品質の維持やスタッフの働きやすさにも寄与します。
人件費に含まれる項目
飲食店の人件費に含まれる主な項目を下表にまとめています。
項目
詳細
所定内賃金
毎月支給する基本給・手当(役職手当や通勤手当など)
所定外賃金
時間外手当、深夜勤務の割増賃金、休日出勤手当など
賞与・一時金
給与とは別に支給する報酬
福利厚生費
社会保険料、社員食堂、社員旅行、特別休暇など
研修・教育費
従業員のスキル向上や資格取得のための費用
退職金
退職金制度に基づく一時的な賃金
飲食店における人件費率の目安
飲食店の人件費率は、一般的に「30%前後」が目安とされています。
ただし、店舗の規模や業態によって適切な人件費率は異なるため、この数値はあくまで目安として捉えるようにしましょう。
人件費率とは、売上高に対する人件費の割合を示す指標です。
【計算式】人件費 ÷ 売上高 × 100(%)
例えば、ある飲食店の月商が200万円で、人件費に60万円かかっている場合、このお店の人件費率は以下のように算出できます。
【計算例】60万円 ÷ 200万円 × 100 = 30%
人件費とFLコストの関係
FLコストとは、食材費(Food)と人件費(Labor)を合わせたコストのことです。これらは飲食店の経費の大部分を占める重要なコストであり、経営者には売上高に占めるFLコストの割合、つまり「FLコスト比率」を常に把握し、適正化することが求められます。
飲食店におけるFLコスト比率の適正値は「60%」といわれています。先述したように、人件費率の目安は「30%」であるため、食材比率・人件費率ともに30%程度に収めるのが理想のFLコスト比率と考えられます。
ただし、実際には業種や業態によってバランスは異なります。例えば、食材費率が20%と低い業態であれば、人件費率が40%になってもFLコスト比率は60%に収まるため、健全な経営ができているといえます。このように、人件費と食材費を個別に見るのではなく、FLコスト全体で管理することが重要です。
飲食店の人件費を最適化する方法

-
飲食店経営においては、人件費を抑えつつサービスの品質やスタッフの定着を維持する工夫が欠かせません。顧客に提供する価値を保ちながら、自店の人件費を最適化するには以下のような方法が考えられます。
- ・人員配置の見直し
- ・オペレーションの改善
- ・システム導入による効率化
- ・スタッフ教育によるスキル向上
- ・業務委託の活用
これらの方法について以下で詳しく解説します。
人員配置の見直し
飲食店の忙しさは、曜日や時間帯によって波があります。ランチやディナーのピーク時には十分な人数のスタッフを配置する必要がありますが、ピーク時以外のアイドルタイムでは、少ない人数でも問題なく対応できるケースが多いでしょう。
こうした変動に合わせてスタッフのシフトや勤務時間を調整すれば、一人ひとりに過度な負担を強いることなく人件費を抑えられます。さらに、スタッフの適性に応じた人員配置を行うことで、業務効率やモチベーションが高まり、残業時間の抑制につながる効果が期待できます。
オペレーションの改善
飲食店の現場では、既存のマニュアルが形骸化し、スタッフそれぞれが独自のやり方で作業を行うことも少なくありません。その結果、無駄な動きや重複作業が生じ、非効率なオペレーションになっていることがあります。
人件費を抑制するためには、現行の業務フローや手順を見直し、オペレーションを最適化することが重要です。無駄な作業が減れば、ミスや手戻りの削減、業務効率の改善につながり、少人数でもスムーズに業務を回せるようになります。新人・ベテランにかかわらず、誰もが一定の基準で業務を遂行できるよう、作業手順やマニュアルを標準化することが大切です。
システム導入による効率化
顧客からの予約や注文、売上集計、在庫管理などを手作業で行っている飲食店では、これらの作業にシステムを導入することで、スタッフの負担を大幅に軽減できます。飲食店においては、以下のようなシステムが業務の自動化・効率化に効果的です。
システム
用途
予約管理システム
電話・Webからの予約受付やキャンセル状況の確認
ハンディターミナル
客席での注文入力やオーダー状況の確認
POSレジ・POSシステム
会計処理や売上集計
在庫管理システム
食品・備品の在庫確認や自動発注
勤怠管理システム
勤務時間の集計や残業・休暇の管理
システム導入には初期投資が必要ですが、長期的に見れば人件費削減と業務効率化の両面での効果が期待できます。
スタッフ教育によるスキル向上
飲食店の人件費を抑えるには、スタッフのスキル向上も欠かせません。全員が一定のクオリティで作業できるよう、現場に即した手順書やマニュアルの整備、ベテランスタッフによるOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)やロールプレイングなど、計画的な教育・指導を行うことが重要です。
スタッフのスキルが向上すれば、顧客に提供するサービス品質も高まり、売上やリピート率に好影響を与えます。また、教育体制が整っている飲食店はスタッフが働きやすく、高い定着率が期待できるため、新しい人材の採用・育成コストの削減にも寄与します。
業務委託の活用
飲食店で発生するすべての業務を店舗スタッフだけで対応している場合は、清掃や調理補助など一部の作業を外部に任せることで、自店での雇用コストを削減できる可能性があります。また、現場管理の手間をなくして経営のみに集中したい場合は、店舗運営そのものを信頼できる第三者に委託するという方法も考えられます。
業務委託を活用すると、採用・育成コストをかけずに、飲食店経験者のノウハウをすぐに活かせるという利点があります。具体的なメリットや雇用との違いについては以下の記事でも詳しく解説していますので、本記事とあわせて参考にしてください。
関連記事:飲食店が業務委託をするメリット・デメリットとは?雇用契約との違いを詳しく解説
新しい飲食店の運営を提案する「店タク」では、飲食店オーナーが独立志向のある職人に店舗運営を委託することを推奨しています。エリア・業態・売上目安などから、お店の現状や条件にマッチするベストパートナーを見つけることができます。
安易な人件費削減が招くトラブル例
人件費を抑えることは経営改善に有効ですが、安易に削減を進めるとさまざまなトラブルに発展するリスクがあります。
ここで言う「安易な人件費削減」とは、短期的にコストを減らすことだけを考え、長期的な経営への影響を考慮しない削減方法を指します。例えば、忙しい時間帯でも最小限のスタッフで回す、十分な教育や研修を行わずに現場に出す、福利厚生を極端に縮小するなど、現場で働くスタッフに大きな負担を強いるような方法がこれにあたります。
具体的にどのような事態が起こり得るのか、飲食店において安易な人件費削減が招くトラブル例を3つ紹介します。
現場の負担増によるミスや事故の発生
-
人件費を無理に削減することは、現場のスタッフに過度な負担を強いることに直結します。人手不足の状態で業務を回そうとすれば、一人あたりの作業量が増え、注文ミスや配膳の取り違え、衛生管理の不備などが発生する可能性が高まります。さらに、包丁や火器による切り傷・やけど、ホール内での転倒による負傷といった労働災害を引き起こすリスクもあります。
こうした事態を防ぐには、適切な人員配置や業務効率化の取り組みが欠かせません。現場の負担を増やさずに、少人数でも安全かつ効率的に業務を遂行できる体制を整えることが重要です。
サービス品質の低下によるクレーム・顧客離れ
-
安易な人件費削減は、スタッフの負担を増やすだけでなく、顧客に提供するサービス品質にも悪影響を及ぼします。人件費を削ったことで人手やスキルが不足すると、料理の提供が遅れたり、オーダーミスが多発したり、味や盛り付けにばらつきが出たりと、サービス品質に直結する問題が起こりやすくなります。
こうした状況が続けば、顧客満足度は著しく低下し、クレームの増加やリピーター離れにつながります。当然ながら売上にも大きな打撃を与えてしまい、本来のコスト削減効果は帳消しになるどころか、かえって経営悪化を招きかねません。重要なのは「削減」ではなく「最適化」であり、オペレーションの改善や教育体制の強化によって、効率的な運営とサービス品質の維持を両立させることが求められます。
スタッフのモチベーション低下と離職リスクの増大
人件費を抑えるために無理なシフトや過重労働を求めたり、反対に極端にシフトを削ったりすると、スタッフの働きがいやモチベーションは低下します。特に、長時間労働は疲労やストレスの原因となり、心身の不調や労災リスク、さらには長期休職や離職につながる恐れがあります。これを防ぐには、需要に応じたシフト管理や個々の適性に合わせた配置、さらには一部業務の外部委託などを取り入れ、スタッフが安心して働ける環境を整えることが重要です。
人件費を抑えつつ従業員満足度を維持する仕組みづくり

-
飲食店経営において、安易な人件費削減はスタッフのモチベーション低下につながるリスクが高く、結果としてサービス品質の低下や離職率の上昇を招く可能性があります。そもそも人材がいなければ経営自体が成り立たないため、現場の状況や負担を無視した強引なコストカットは絶対に避けるべきです。
飲食店が人件費の抑制に取り組むうえでは、まずスタッフが働きやすい環境や体制を整えることが前提となります。無駄を省いた効率的なオペレーションやシステムによる作業の自動化に加え、透明性の高い評価制度やインセンティブの導入、個々のスキルアップを後押しする教育・研修機会の提供など、スタッフの負担軽減とモチベーション維持を両立させる施策が求められます。
こうした取り組みはスタッフの定着を促進し、業務効率やサービス品質の向上にも寄与します。その結果、無理のない人件費の最適化が可能となり、安定した経営基盤の構築につながることが期待できます。
まとめ
飲食店の人件費率は「30%程度」が目安とされ、店舗にとっては食材費と並ぶ大きなコストとなります。人件費率が高い場合には、利益率の低下や設備投資への資金不足などが起こりやすい一方で、安易な削減はスタッフのモチベーションやサービス品質を低下させ、さらには離職増加や顧客離れのリスクを高める可能性があります。人件費の節約は“短期的なコストカット”に走らず、現場の状況やスタッフの働きやすさを考慮し、慎重に対応していくことが重要です。
店タクは飲食店オーナーが抱える店舗運営の悩みを「職人と組む」ことで解決するサービスです。人件費が経営を圧迫しているなら、信頼できる第三者に店舗運営を委託する選択肢もぜひご検討ください。
-
-
飲食店の運営
飲食店売却の基本|種類・相場・閉店手続き・注意点をわかりやすく解説

飲食店を手放したいと考えたとき、今後の選択肢の一つに「売却」があります。売却手続きを進める際は、一般的な価格相場や手続き上の注意点を理解しておくことが、後々のトラブルや損失を防ぐことにつながります。
この記事では、飲食店売却を考えているオーナーが押さえておくべき基礎知識を解説します。売却の種類や相場、手続きの流れを把握し、計画的に準備を進めましょう。
飲食店売却の種類とメリット・デメリット
飲食店を売却する方法には、大きく「居抜き売却」と「M&A(事業譲渡/株式譲渡)」の2種類があります。どの方法が適しているかは、店舗の状況や売却の目的によって異なります。まずは、それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分のケースに当てはめて考えてみましょう。
居抜き売却
居抜き売却とは、店舗内の設備や内装を残したまま、居抜きの状態で次の経営者に引き継ぐことです。個人経営の飲食店では一般的な売却手段であり、コストを抑えながら店舗をスムーズに引き渡すことができます。
居抜き売却のメリット・デメリットは次のとおりです。
メリット
- ・設備の処分費や原状回復工事費を抑えられる
- ・引き渡しの直前まで営業を続けられる
- ・造作譲渡料を得られる
居抜き売却では設備や内装も丸ごと引き渡すため、売却前の解体工事が必要ありません。これにより撤退費用を抑えられるほか、手続きが行われている間も通常通りに営業を続けることが可能で、解約予告期間中の賃料を削減できるメリットもあります。
デメリット
- ・店舗の立地や評判が売却価格に影響しやすい
- ・スタッフに売却計画を知られる可能性がある
- ・契約条件や設備の状態によってはトラブルになりやすい
居抜き売却では、店舗の立地や評判が買い手の判断に直結するため、条件によっては売却価格が下がることがあります。また、早い段階で閉店計画がスタッフに伝わってしまうと、働くモチベーションが低下し、人材流出につながることも懸念されます。
M&A(事業譲渡/株式譲渡)
M&Aとは「合併(Mergers)と買収(Acquisitions)」を意味し、主な手法に「事業譲渡」や「株式譲渡」があります。居抜き売却は設備や内装だけを譲渡するのに対し、M&Aは事業や会社そのものを引き継ぐ形で、事業ノウハウや従業員などの無形資産も含めて包括的に譲渡できるのが特徴です。
· 事業譲渡:事業の一部または全部を第三者に譲渡する方法
· 株式譲渡:保有株式を第三者に譲渡し、経営権を移転させる方法
M&Aのメリット・デメリットは次のとおりです。
メリット
- ・高額売却が期待できる
- ・スタッフの雇用を守れる
- ・取引先との関係を維持できる
- ・後継者問題が解消する
M&Aでは事業全体を引き継ぐため、従業員や取引先との関係を保ちながら、将来の収益力まで含めて評価されます。後継者不足を理由に撤退を検討している場合も、事業や会社を次のオーナーに引き継ぐM&Aが有力な選択肢となるでしょう。
デメリット
- ・譲渡までに時間がかかる
- ・買い手が限定される
- ・顧客や取引先との関係が悪化する可能性がある
M&Aは事前調査や契約交渉に時間を要し、居抜き物件と比べて買い手も限定されやすい点がデメリットとなります。また、経営方針や取引条件の見直し、ブランドイメージの変化などにより、顧客や取引先との信頼関係が損なわれる可能性があります。
飲食店売却の相場価格

-
飲食店を売却する際、どのくらいの価格で売れるのかは気になるポイントです。ここでは、居抜き売却とM&Aの相場感を紹介し、売却価格の目安や算出方法をわかりやすく解説します。
居抜き売却の相場価格
居抜き売却の相場価格は、20坪程度の小規模な店舗で50〜150万円程度(東京都内)といわれています。ただし、実際には店舗規模や設備の状態、立地条件などさまざまな要素によって変動するため、あくまで一般的な目安として考えてください。
また、売却価格の目安として、「坪単価」(1坪あたりの月額家賃)の60〜100倍を参考にする方法もあります。例えば、25坪の店舗で月額家賃が45万円の場合、1坪当たりの単価は1.8万円です。これの60〜100倍と考えると、売却価格の目安はおよそ108万〜180万円となります。
M&Aの相場価格
M&Aでの飲食店売却では、有形資産・無形資産を含めて事業や会社全体の価値が評価されます。明確な相場はありませんが、一般的には「時価純資産+営業利益の2〜5年分」が目安となります。
例えば、時価純資産が800万円、年間営業利益が300万円の場合、M&Aによる売却価格は以下のように試算できます。
計算例
【最小ケース(営業利益×2年)】
800万円 + 300万円 × 2
= 800万円 + 600万円 = 1,400万円
【最大ケース(営業利益×5年)】
800万円 + 300万円 × 5
= 800万円 + 1,500万円 = 2,300万円
このケースでは、1,400〜2,300万円ほどが相場となります。
今後の収益性が反映される分、居抜き売却よりも高額になる傾向がありますが、最終的な価格はデューデリジェンス(対象企業の価値やリスクを事前に調査するプロセス)の結果や契約交渉によって決まります。
売却価格に影響を与える要素
飲食店の売却価格は、設備や内装以外にもさまざま要素が影響します。
相場を左右する主なポイントは次のとおりです。
- ・立地:駅前や商業施設の近くなど、買い手のニーズが大きいエリア
- ・店舗の規模:面積や席数が適切で、効率的に運営できる店舗
- ・店舗の状態:内装や設備の状態が良好で、清潔感のある店舗
- ・売上・利益の実績:安定した収益を得ている店舗
- ・ブランド力:地域での認知度や評判、口コミ評価など
これらの要素は事前に改善できる部分も多いため、店舗の現状を見直しつつ、必要な準備をしておくとよいでしょう。取り組み次第では買い手からの評価が高まり、売却価格をより有利に設定できる可能性があります。
閉店・廃業時に必要な手続き
飲食店を閉店・廃業する際には、関係者への通知や行政手続きまで、さまざまな対応が必要となります。これを怠ると、後々トラブルや余計な費用が発生することがあるため、早いうちから手続きを整理して計画的に進めましょう。
下記は閉店・廃業時に行う手続きの一例です。
閉店・廃業前の準備
- ・スタッフへの解雇通知
- ・不動産会社への解約通知
- ・取引先への通知
- ・各種契約の解約手続き
閉店・廃業後の対応
- ・店舗の原状回復工事
- ・設備の撤去・返却
- ・税務署や保健所への届出
なお、売却や譲渡を選択する場合は不要となる手続きも多く、閉店に伴う手間や費用を減らしながらスムーズに事業を引き渡すことができます。
飲食店の閉店・廃業時に必要な届出については下表を参考にしてください。
閉店・廃業に伴う手続き(一例)
提出期限
届出書(提出先)
廃業日から5日以内
健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届(年金事務所)
健康保険・厚生年金保険被保険者喪失届(年金事務所)
廃業日から10日以内
廃業届/食品営業許可証の返還(保健所)
事業開始(廃止)等申告書(都道府県税事務所)
廃業日翌日から10日以内
雇用保険適用事業所廃止届(公共職業安定所)
雇用保険被保険者資格喪失届(公共職業安定所)
雇用保険被保険者離職証明書(公共職業安定所)
廃業日から1カ月以内
個人事業の開業・廃業等届出書(税務署)
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(税務署)
廃業日翌日から50日以内
労働保険確定保険料申告書(労働基準監督署)
廃業後速やかに(※)
消費税の事業廃止届出書(税務署)
防火管理者選任(解任)届出書(消防署)
※法的期限はないものの、遅滞なく速やかに届け出る必要がある
飲食店の閉店・廃業手続きについては以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:「店をたたむ」と決断したら|飲食店オーナーが知っておくべき手続きの流れと再出発の選択肢
飲食店を売却するときの注意点
飲食店売却にあたって押さえておくべきポイントを解説します。対応を誤るとトラブルにつながる恐れがあるため、売却時の注意点を事前に把握しておきましょう。
売却できるもの・できないもの
居抜き売却の場合、どこまでが売却の対象となるのかを明確にしておくことが重要です。基本的には、売り手に所有権がある厨房設備や什器、家具、内装などは売却対象となります。一方で、食材や調味料などの消耗品は衛生管理の観点から譲渡できず、事前に処分しておく必要があります。
また、リース契約で利用している機器類も売却対象外です。これらは契約上リース会社に所有権があるため、売り手が勝手に売却することはできません。ただし、買い手がリース契約を引き継ぐ形で調整できるケースもあります。
居抜き物件の「原状回復義務」
原則として、賃貸借契約には「退去時に原状回復を行う」義務が定められています。ただし、居抜きで退去する場合は旧貸借人(売り手)の原状回復義務が免除され、新貸借人(買い手)がこの義務を負うことになるのが一般的です。
とはいえ、居抜き物件では「原状」がどの状態を指すのかがわかりにくく、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。これを防ぐには、契約書に「退去予定者は原状回復義務が免除される」旨を明記し、内装や設備の引き渡し範囲についても事前に細かく取り決めておくのが望ましいでしょう。
営業許可・賃貸借契約
居抜き売却や事業譲渡の場合、飲食店の営業許可は譲渡できず、原則として買い手による再取得が必要です。一方、株式譲渡であれば法人自体は存続するため、営業許可はそのまま継続されます。
また、賃貸借契約に関しては「譲渡禁止条項」が盛り込まれているケースも多く、貸主の承諾がなければ引き継げない可能性があります。そのため、売却や譲渡を検討する際には、事前に貸主の許可を得ておくことが不可欠です。
飲食店売却をお考えの方に

-
事業撤退を考えるとき、その手段は売却や譲渡だけではありません。経験豊富なパートナーに店舗運営を委託し、事業を継続していく選択肢もあります。「お店は維持したいが、自分で運営するのは難しい」と感じている経営者にとって、業務委託による第三者への引き継ぎは有効な選択肢となるでしょう。
飲食店が業務委託を結ぶメリット
-
飲食店が業務委託をする場合、スタッフの採用・育成コストがかからず、経験者のノウハウをすぐに活用できるメリットがあります。将来的に売却や譲渡を考えている場合でも、事業を継続すれば安定した収益が得られるため、判断を焦らず適切なタイミングを見極めることができます。
飲食店の業務委託については以下の記事でも詳しく解説しています。
店舗運営を委託するなら「店タク」
店タクは、「お店を任せたい人」と「お店を持ちたい人」を業務委託という仕組みでつなぐマッチングサービスです。人手不足や売上低迷など、飲食店オーナーが抱える店舗運営の悩みは「独立志向の強い職人と組む」ことで解決できます。
店タクは「任せたい」「挑戦したい」という明確な意志を持った方が利用しています。運営委託に興味のある経営者の方は以下のサービスサイトをぜひご覧ください。
まとめ
飲食店を売却する方法には、主に「居抜き売却」と「M&A(事業譲渡/株式譲渡)」があります。居抜きは設備や内装を残したまま引き渡すため、コストを抑えながら短期間で譲渡できるのが特徴です。一方、M&Aは事業や法人ごと引き継ぐため、売却価格が高くなりやすく、スタッフや取引先との関係を維持しやすいメリットがあります。
また、売却や譲渡だけでなく、信頼できる人材に店舗運営を委託するのも一つの方法です。それぞれの特徴や注意点を理解したうえで、オーナーの希望や自店の状況に合う最適な方法を選択することが大切です。
店タクは、飲食店オーナーが抱える店舗運営の悩みを「職人と組む」ことで解決するサービスです。売却や譲渡を決断する前に、信頼できる第三者に“店舗運営を委託する”という選択肢も検討してみてはいかがでしょうか。
-
飲食店の運営
飲食店の平均売上は?業種別のデータや計算方法、売上低迷時の改善策を詳しく解説

飲食店は競争が激しい業界であり、安定した経営を続けるには売上予測を立てることが重要です。実際の売上が予測を下回る場合はその原因を探り、早急に対策を講じる必要があります。まずは「自店の売上はいくらか」「どのくらいの売上が必要か」を把握することから始めましょう。
この記事では、飲食店の平均売上や計算方法とともに、売上が低迷する原因とその改善策について詳しく解説します。自店の状況と照らし合わせながら、必要な改善の方向性を考えてみてください。
【業種別】飲食店の平均売上
日本政策金融公庫のデータをもとに、飲食店の平均売上(従業員1人当たりの売上高)を下表にまとめました。この表では一般飲食店を「食堂/レストラン」「そば・うどん店」「すし店」「喫茶店」「その他の一般飲食店」の5業種に分類し、それぞれの業種の平均売上をまとめています。
業種
従業者1人当たり売上高
食堂/レストラン
926万円
そば・うどん店
759万円
すし店
1,007万円
喫茶店
876万円
その他の一般飲食店
1,039万円
※千円未満切り上げ
また、同データにおける一般飲食店(上記5業種)の平均売上は「923万円」となっています。上表のとおり業種によって多少異なるものの、一般的な飲食店の平均売上は年間で「900万円強」(従業員1人当たり)といえそうです。
例えば、1〜2人体制で経営する個人飲食店であれば、年間で1,000〜2,000万円ほどの売上が目安となるでしょう。この場合の「1日・月・年間」の平均売上を下表にまとめましたので、それぞれどのくらいの売上が必要となるのか参考にしてみてください。
【個人飲食店の売上目安】
1日の平均売上
2.7〜5.5万円
月の平均売上
83〜167万円
年間の平均売上
1,000〜2,000万円
店舗規模や立地による売上の違い
飲食店の平均売上は「年間900万円強」と説明しましたが、これはあくまで統計上の数値にすぎません。実際の店舗売上は、業種や規模、立地条件など、さまざまな要素によって大きく変動します。あくまで一つの目安と捉え、自店の状況に合わせた判断が必要です。
次項では、飲食店の平均売上をどのように算出するのか、その計算方法を解説します。実際のケースを想定し、自店の目安となる平均売上を計算してみましょう。
飲食店における平均売上の計算方法

-
ここでは、目安となる平均売上(売上予測)の計算方法を解説します。実際の店舗経営において売上は日ごとに変動しますが、まずは基本となる計算方法を押さえておきましょう。
売上の計算式
飲食店の1日当たりの売上は次の計算式で算出できます。
売上 = 客単価 × 席数 × 回転数
売上は「客単価」「席数」「回転数」の掛け合わせとなるため、客単価が高くても席数や回転数が少なければ売上は伸びにくく、反対に客単価が低くても席数や回転数が多ければ売上アップにつながりやすくなります。
月間売上のシミュレーション
水曜定休のレストラン(ランチ/ディナー営業)を想定し、1か月の売上金額をシミュレーションしました。自店の状況に当てはめて算出すれば、現状の月間売上を、客単価や回転数を調整することで目安となる平均売上を把握できます。
区分
1日の売上
営業日数
月間売上
昼(月〜金)
900円 × 20席 × 0.6回転 = 10,800円
16日
172,800円
昼(土日)
1,000円 × 20席 × 0.8回転 = 16,000円
8日
128,000円
夜(月〜木)
3,000円 × 20席 × 0.8回転 = 48,000円
12日
576,000円
夜(金〜日)
4,000円 × 20席 × 1.0回転 = 80,000円
12日
960,000円
合計
1,836,800円
売上を伸ばすために必要な3つの視点
飲食店が売上を伸ばすためには、「客数」「客単価」「リピーター」の3つの視点から、日々の運営や戦略を見直していくことが重要です。単に売上目標を設定するだけではなく、要素ごとに具体的な施策をバランスよく講じることが、継続的に安定した売上を確保するための鍵となります。
ここでは、飲食店が重視すべき3つの視点について詳しく解説します。
客数を増やす
売上を伸ばすうえで基本となるのが「客数」を増やす施策です。飲食店が新規顧客を呼び込むためには、消費者からの認知度を高める施策が必要です。SNSを使った情報発信や近隣へのチラシ配布、イベント出店など、オンライン・オフライン両方の集客施策を行い、お店の強みや魅力を積極的にアピールしましょう。
また、一度来店したことのある既存顧客に対し、次の来店を促すことも重要です。新規顧客だけに注力せず、既存顧客をターゲットとした集客施策もあわせて行い、売上の安定化を目指しましょう。
客単価を上げる
飲食店が売上を伸ばすには、客単価を上げる施策も欠かせません。同じ客数であっても、客単価が上がれば売上も伸びるため、一人当たりの支出を増やす工夫が必要です。
客単価アップにつながる施策には以下のようなものがあります。
- ・メニュー価格を値上げする
- ・注文に関連したセットメニューを提案する
- ・特別なコースへのグレードアップを促す
- ・高価格帯のメニューを取り入れる
重要なのは、売上と同時に顧客満足度も高めることです。単なる値上げや押し付けではなく、「顧客に価値を感じてもらえる提案」を行い、自然な形で客単価を上げることが大切です。
リピーターを育てる
飲食店経営を継続するうえで、一時的な売上増加では意味がありません。売上を安定させるには、自店のメニューやサービスに好感を持ち、繰り返し来店してくれる「リピーター」の育成が不可欠です。
具体的な施策としては、既存顧客を対象とした特典やポイントカードの導入、期間限定クーポンの発行などが考えられます。スタッフが名前を覚えて声をかけたり、好みに合ったメニューを提案したりするのも効果的です。顧客に「また行きたい」と思ってもらえるよう、接客の質や店舗の体験価値を高める工夫を行いましょう。
飲食店が平均売上を下回るときの原因と改善策

-
飲食店の売上が平均を下回る場合、主な原因としては「集客不足」「客離れ」「経費の高騰」が考えられます。「売上がなかなか伸びない」「一時的に上がってもすぐに落ちてしまう」などの課題がある場合は、これら3つの観点から売上低迷の原因を特定し、具体的な改善策を講じることが重要です。
-
【集客不足】顧客の来店動機をつくる
-
集客不足を改善するためには、お客様が店舗に来店する動機をつくることが大切です。多くの選択肢があるなかで、「あのお店に行きたい」と思ってもらうには、魅力的なメニュー開発や期間限定のキャンペーンなど、顧客の来店動機となる施策を打ち出していく必要があります。
また、InstagramやLINE公式アカウントを通じて定期的に情報を発信したり、Googleビジネスプロフィールの内容をアップデートしたりと、オンライン上での店舗の存在感を高める施策も効果的です。これらの施策を通じて“来店のきっかけ”を増やすことが、安定した集客基盤の構築につながります。
【客離れ】QSC(品質・サービス・清潔さ)改善で再来店を促す
QSCは飲食店が重視すべき基本的な要素であり、「Quality(品質)」「Service(サービス)」「Cleanliness(清潔さ)」の頭文字を取っています。これらは顧客満足度に大きく影響し、リピーターを育てるうえでも欠かせない要素です。一度きりの来店で終わってしまうことが多く、なかなか再来店につながらない場合は、以下のような施策を取り入れてQSCの改善・向上を目指しましょう。
Quality(品質)を高める施策
- ・旬の食材や地域の特産品を使ったメニューを開発する
- ・料理の味や盛り付けを安定させる
- ・レシピや調理手順を標準化する
Service(サービス)を高める施策
- ・ベテランスタッフによるOJTで接客の質を向上させる
- ・キャッシュレス決済やオンライン予約システムを導入する
- ・オペレーションの見直し・改善を行う
Cleanliness(清潔さ)を高める施策
- ・店内の清掃を徹底する
- ・食品・食器の衛生管理を徹底する
- ・清掃・消毒のタイミングを記録する
【経費の高騰】適正な原価管理や人員配置でコストを抑える
原材料費や人件費などの経費の高騰は、飲食店の利益を大きく圧迫する要因となっています。これに対応するためには、仕入れ先の見直しや適切な価格設定、人員配置の最適化、ツール導入による業務効率化などに取り組み、コストを抑えながらも料理やサービスの品質を維持することが大切です。従来の価格を続けるよりも、状況に応じた価格調整やコスト管理を行い、無理なく利益を確保することを目指しましょう。
以下の記事でも飲食店が売上を上げる方法について詳しく解説していますので、自店に必要な施策を考えるときの参考にしてください。
関連記事:売上を上げる方法とは?飲食店が取り組むべき施策と売上アップの原則を徹底解説
「施策を講じてもなかなか売上につながらない」
「売上が伸びても一時的で、すぐに客足が途絶えてしまう」
──このようなお悩みがあれば、店タクで経験豊富なパートナーに店舗運営を任せる選択肢もぜひ検討してみてください。店タクなら、エリア・業態・売上目安などから、あなたの条件にマッチするベストパートナーを見つけることができます。
飲食店経営における「売上以外」の重要指標
飲食店経営においては、売上以外にも重視すべき指標がいくつかあります。
ここでは、飲食店オーナーが特に把握しておくべき「FL比率」「営業利益率」「損益分岐点売上高」について解説します。
FL比率
FL比率とは、売上に対する「食材費」と「人件費」の割合のことです。
一般的な飲食店のFL比率は60%程度といわれており、この値が高いほど利益は圧迫され、低いほど経営に余裕が生まれることになります。飲食店が利益率を高めるためには、売上に対してどのくらいFLコストがかかっているかを把握し、適切なコスト管理を行うことが重要です。
FL比率を算出する計算式は次のとおりです。
FL比率 =(食材費 + 人件費)÷ 売上高 × 100
営業利益率
営業利益とは、粗利益から営業活動にかかる経費を差し引いた利益のことです。
売上に対する営業利益の割合を「営業利益率」といい、店舗の収益性を測る指標として活用できます。
営業利益率を算出する計算式は次のとおりです。
営業利益率 (%) = (営業利益 ÷ 売上高) × 100
損益分岐点売上高
損益分岐点とは、売上と経費が同額で、利益がちょうどゼロになる売上高のことです。
これを算出することで売上が経費を上回る(=黒字になる)水準がわかり、店舗経営の健全性を測る指標として活用できます。
損益分岐点売上高を算出する計算式は次のとおりです。
損益分岐点売上高 = 固定費 ÷(1 − 変動費率)
(※変動費率 = 変動費 ÷ 売上高)
飲食店の利益率や損益分岐点については以下の記事でも詳しく解説し、実際の数値を用いたシミュレーションを行っています。本記事とあわせて参考にしてください。
関連記事:飲食店の利益率とは?計算方法・低い原因・改善策をまとめて解説
まとめ
一般的な飲食店の平均売上は、従業員1人あたり「年間900万円強」とされています。ただし、この数値はすべての店舗に当てはまるものではなく、業種や店舗規模、立地条件などによって大きく変動します。あくまで目安として捉え、自店の状況に基づいた売上予測を算出することが大切です。
そして、実際の売上が予測を下回っている場合には、集客施策やサービス内容、コスト構造などを見直し、早めに改善策を講じる必要があります。短期的な売上回復だけにとらわれず、長期的な安定経営を見据えることが重要です。
店タクは飲食店オーナーが抱える店舗運営の悩みを「職人と組む」ことで解決するサービスです。売上低迷や人材不足にお悩みなら、腕のある職人に店舗運営を委託することも有効な選択肢となります。
-
-
飲食店の運営
「店をたたむ」と決断したら|飲食店オーナーが知っておくべき手続きの流れと再出発の選択肢

飲食店経営は売上の波が大きく、時には「店をたたむ」という決断が必要になることもあります。計画的に閉店作業を進め、次の挑戦へつなげるためには、必要な手続きの内容や流れをあらかじめ把握しておくことが大切です。
この記事では、飲食店をたたむ際の手続きや閉店にかかる費用、再出発の選択肢について解説します。具体的なステップや注意点を理解することで、不要なやりとりやトラブルを防ぎ、余裕を持って次なる一歩を踏み出すことができます。
「店をたたむ」前に知るべきサイン

-
飲食店経営を続けるなかで、撤退を検討すべきサインはいくつか存在します。閉店・廃業する飲食店にはどのような兆候があるのか、ここでは「店をたたむ」前に知るべき4つのサインを紹介します。
看板メニューの売上が落ちている
集客の柱ともいえる「看板メニュー」の売上が落ちている場合、お店の魅力や強みが薄れ、集客力が低下しているサインといえます。これまで人気だった看板メニューの売れ行きが悪くなるのは、味や品質の劣化、顧客ニーズやトレンドの変化、競合店の登場などさまざまな要因が考えられます。
全体の売上が許容範囲にあるなら、すぐに「店をたたむ」決断に直結することはないかもしれません。しかし、そのまま放置するといずれは他のメニューにも悪影響が及ぶおそれがあるため、メニューの改良や販促強化といった対策を早急に打ち出す必要があります。
赤字が慢性化している
数か月にわたり赤字が続いている場合は、店舗を維持するための運転資金が急速に枯渇し、いずれは「店をたたむ」決断を余儀なくされるでしょう。無理に営業を続けることは経営リスクを増大させ、資金不足による支払遅延やトラブルの発生など、深刻な問題を引き起こすおそれがあります。
まずは原価管理やメニュー改定、固定費の見直しなどで改善の余地があるのか検討し、それでも黒字化の兆しが見えない場合には早めに撤退を判断するほうが、その後の再出発の可能性が広がっていくと考えられます。資金不足はスタッフや取引先へ与える影響が大きいため、早めに現状を把握し、撤退も視野に入れた判断を下すことが重要です。
店内の清掃が行き届いていない
-
QSC(品質・サービス・清潔さ)は、飲食店が重視すべき基本的な要素です。清掃が十分に行き届いていない状態は、見た目の印象や顧客からの信頼を損なうだけでなく、経営者やスタッフのモチベーション低下を映し出すサインともいえます。
忙しさで掃除が後回しになっていることも考えられますが、そのまま放置すれば店内の雰囲気は確実に悪化します。清潔感のない店舗は顧客からのクレームに直結しやすく、ネガティブな口コミが広がれば新規顧客の来店が減少し、いずれは常連客の離脱も招くことになるでしょう。
-
常連客が離れている
-
安定した売上の基盤となる「常連客」が離れるのは、顧客ニーズとのズレが進行しているサインであり、改善しなければ「店をたたむ」判断が現実味を帯びてくるでしょう。常連客は不満があってもすぐに店を離れるのではなく、具体的な要望や改善点を伝えてくれることが多いため、その声を“改善のヒント”として真摯に受け止めることが大切です。
ただし、立地や周辺環境の変化などに起因し、客層が入れ替わっていることも考えられます。この場合は新しいターゲット層に合わせたメニュー開発や情報発信を行うことで、売上を維持・回復できる可能性があります。
「いつ閉めるか」が再出発のカギ−適切なタイミングとは?
再出発を成功させるためには、次の挑戦への余力を残すことが重要です。あらかじめ撤退ライン(=損切りライン)を決めておくと、売上や利益が一定水準を下回った時点で「撤退するか否か」を客観的に判断できます。閉店・廃業するにも費用がかかるため、その資金を確保できる段階で撤退を決めるのが望ましいでしょう。
また、体力や気力が十分にあるうちに判断することで、閉店後も冷静に次の挑戦に取り組む余裕が生まれます。再出発をスムーズに進めるためにも、損失を最小限に抑えられるタイミングを見極めることが大切です。
店タクは飲食店オーナーが抱える店舗運営の悩みを「職人と組む」ことで解決するサービスです。「店をたたむ」と決断する前に、業務委託でつながる「新しい店舗運営」を検討してみませんか。
店をたたむときの手続きと閉店費用
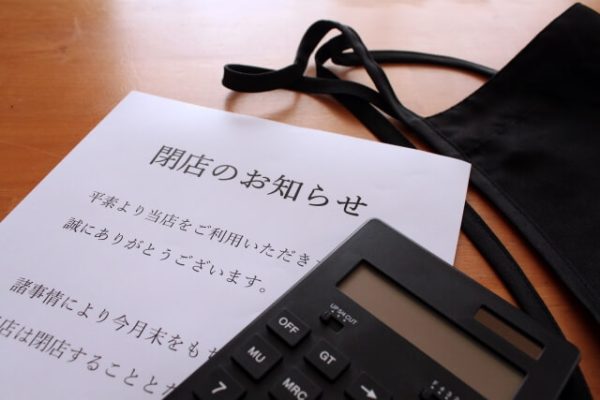
-
飲食店を閉めるときには多くの手続きを伴い、閉店にかかる費用を事前に用意しておく必要があります。ここでは、店をたたむときの準備と手続きの流れ、閉店費用について解説します。
-
店をたたむ前にするべき準備
-
店をたたむ前には、関係各所への通知や手続きを計画的に行うことが重要です。
- ・スタッフへの解雇通知
- ・不動産会社への解約通知
- ・仕入れ先やリース業者など取引先への通知
- ・電気・水道・ガス・インターネットなどの解約手続き(最終使用日の調整)
- ・顧客への告知
特に注意すべきはスタッフへの対応です。使用者が労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇を予告する必要があります(労働基準法第20条より)。これを怠り、解雇の予告を行わない場合には、30日以上分の平均賃金を「解雇予告手当」として支給しなければなりません。また、解雇予告の日数が30日に満たない場合も、その不足日数分の平均賃金を支払う必要があります。
店をたたむときの手続きの流れ
閉店・廃業当日以降は、店舗の原状回復や設備の撤去・返却を行うほか、さまざまな行政手続きが必要となります。それぞれ提出期限が決められているため、事前に内容を確認し計画的に進めていくことが大切です。
- 閉店・廃業に伴う手続き(一例)
提出期限
届出書(提出先)
廃業日から5日以内
健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届(年金事務所)
健康保険・厚生年金保険被保険者喪失届(年金事務所)
廃業日から10日以内
廃業届/食品営業許可証の返還(保健所)
事業開始(廃止)等申告書(都道府県税事務所)
廃業日翌日から10日以内
雇用保険適用事業所廃止届(公共職業安定所)
雇用保険被保険者資格喪失届(公共職業安定所)
雇用保険被保険者離職証明書(公共職業安定所)
廃業日から1か月以内
個人事業の開業・廃業等届出書(税務署)
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(税務署)
廃業日翌日から50日以内
労働保険確定保険料申告書(労働基準監督署)
廃業後速やかに(※)
消費税の事業廃止届出書(税務署)
防火管理者選任(解任)届出書(消防署)
※法的期限はないものの、遅滞なく速やかに届け出る必要がある
閉店にかかる費用
閉店・廃業時にかかる主な費用は次のとおりです。
- ・原状回復費
- ・退去までの家賃
- ・リースの残額料金
- ・廃棄処分費
- ・後払いの経費や借入金の返済
- ・解雇予告手当(必要な場合)
これらの費用は閉店に伴って発生するため、あらかじめ資金を確保しておくことが重要です。保証金が返還される場合は実質的にプラスになることもありますが、物件を明け渡したあとに返ってくるお金であるため、当面必要となる費用は自己資金で賄えるよう準備しておきましょう。
【飲食店向け】再出発の選択肢とその手順
「店をたたむ」ことを決断しても、すぐに完全撤退するのではなく、店舗や事業を活かしながら再出発を目指す方法もあります。その代表的な選択肢として挙げられるのが「業態転換」と「運営委託」です。
再出発の選択肢①:業態転換
業態転換とは、より収益性や需要のある形態に切り替える方法です。市場ニーズに合わせた新しい業態に挑戦することで、既存の店舗資産や経営ノウハウを活かしながら新しい顧客層を取り込み、経営改善につなげられる可能性があります。
飲食店における業態転換の基本的な手順は次のとおりです。
- 1.市場調査と現状分析
- 2.コンセプト・事業計画の策定
- 3.オペレーションの設計
- 4.実行・評価
これらのステップを踏むことで、感覚的な判断ではなく、データや計画に基づいた転換が可能になります。新業態を安定させるためには、リリース後も定期的に評価し、必要に応じて改善を重ねることが大切です。
再出発の選択肢②:運営委託
運営委託とは、自らは運営から退き、信頼できる第三者に店舗運営を任せる方法です。「店は残したいが、自分で運営するのが難しい」と感じている経営者にとって有効な選択肢となります。
飲食店における運営委託の基本的な手順は次のとおりです。
- 1.委託先の選定
- 2.契約内容の取り決め(必要に応じて内見・打ち合わせを実施)
- 3.業務委託契約の締結
- 4.運営開始と定期的なフォロー・評価
運営委託では、信頼できる委託先を選定し、双方合意のもとで報酬や営業ルールを取り決めるのが一般的です。飲食店の業務委託については以下の記事で詳しく解説していますので、運営委託を検討する際の参考にしてください。
関連記事:飲食店が業務委託をするメリット・デメリットとは?雇用契約との違いを詳しく解説
まとめ
飲食店の閉店・廃業には、関係各所への届出やスタッフへの告知、原状回復工事などさまざまな手続きを伴います。再出発を目指す場合は、体力や気力、資金が残っているうちに「店をたたむ」決断を下すことが重要です。
また、完全にお店を閉じる前に、業態転換や運営委託で再挑戦する選択肢も考えられます。既存の店舗やノウハウを活かしつつ、新しい市場や顧客ニーズに柔軟に対応することで、事業を継続できる可能性が高まるでしょう。どの方法を選ぶにせよ、閉店の決断も戦略の一つと捉え、次の挑戦に向けて前向きに行動することが大切です。
店タクでは「店舗運営を任せたいオーナー」と「腕のある職人」とのマッチングを支援しています。自分で経営を続けるのは難しいと感じている場合は、信頼できる職人に店舗運営を委ねるという選択肢もあります。
-
 飲食店運用のヒント
飲食店運用のヒント